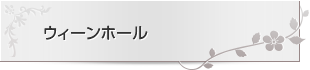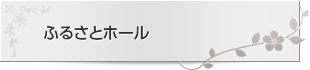劇場一口メモ
『パイプオルガン』
海を渡って来た芸術劇場の顔

ウィーンホール舞台正面にそびえ立つ壮大なスケールのパイプオルガンは、まさに劇場の“顔”と言ったところでしょうか。
ドイツにあるヒンリッヒ・オットー・パーシェン社製のこのパイプオルガンは、劇場オープンの1991年6月を目指し、ドイツでパイプをはじめとするパーツが製作され、海を渡り約3か月間かけて丹念に組み上げられました。
高さ10メートル、幅5.7メートルのパイプオルガンには大小様々なパイプが組み込まれ、なんとその数は3,636本、おもてに見えるのはほんの一部です。
音響性能を重視したシューボックススタイルの抜群の響きは、暖かな木質で統一されたホールに、深みのある音色を響かせます。2010年の芸術劇場改修工事にあわせ、全面的なオーバーホールを実施しました。
『スタインウェイD-274』
世界最高のピアノはすべて手作り

スタインウェイサンズ社は、ヘンリー・エンゲルハルト・スタインウェイが開設して以来、150年以上という長い歴史を持っています。
多種あるスタインウェイ製のピアノの中でも、フラッグシップと言えるフルコンサート仕様がこのD‐274で、どりーむホールとウィーンホールに計3台があります。
劇場がオープンを間近に控えた1991年5月に、当時港区にあった松尾楽器商会のショールームで、この日のために用意された数あるD-274の中から、ピアニストの中村紘子さんが全台を試奏したうえで選んだものです。
調律、オーバーホールを重ね、その音色はさらに深みを増しています。
『ベーゼンドルファー フルコンサート275型』
今も変わらない音楽家たちが愛した本物の音色

ウィーンホールにあるベーゼンドルファー社の「フルコンサート275型」は芸術品とも称され、その特徴は、鍵盤数が普通88鍵であるのに対し92鍵と大きく、低音側に広げられた鍵盤は標準音域と区別するため、黒く塗られているのが特徴です。
このピアノの芸術品とも称されるベーゼンドルファーの名を一躍有名にしたのはピアノの魔神といわれたリストで、当時の彼のピアノに対する高い要求に答え、かつすさまじい腕力と技巧に耐えられた唯一のピアノだったと言われています。
1828年ウィーンで生まれたこのピアノは、以来決して量産されることなく、熟練工による伝統的工法にこだわり、リストをはじめブラームス、J.シュトラウスIIなど多くの音楽家に愛され、今もなお聴衆を魅了してやみません。
『チェンバロ(フレンチダブルマニュアルハープシコード)』
バロック時代を代表する鍵盤楽器

イタリア語ではチェンバロ、英語ではハープシコード、フランス語ではクラヴサンと呼ばれるこの楽器。
ウィーンホールのものは、アトリエ・フォン・ナーゲル社製の二段鍵盤で、楽器の特徴は、美しい装飾にもありますが、ピアノがキイを押してハンマーで弦を打つのに対し、チェンバロはキイを押しジャックと呼ばれる細長い木片につけられたプレクトラム(鳥の羽の芯や皮革で作られた爪状のもの)が、弦を下から上へ引っ掻く様にして音を出します。
14世紀頃にイタリアで発明されたと言われ、劇音楽の誕生した16世紀初頭から18世紀中頃のバロック時代を代表する鍵盤楽器で、音の強弱をつけたり和音を弾くには制限があるため、ベートーヴェン以降のピアノ曲は演奏できませんが、バッハの鍵盤作品や17~18世紀のクラヴサン音楽では、優雅で繊細な音色が際立ちます。
『残響可変装置』
432本の白い筒は音の魔術師

ウィーンホールを見上げると天井には432本の白い筒状の棒がありますが、これは残響可変装置といいます。
カラオケのときにリバーブ(エコー)をかけたり、風呂場で歌ったりすると気持ちよく感じるのは、残響が心地よく響くからで、この装置はもともと響きを重視して造られたウィーンホールの残響を、きめ細かくコントロールするためのものです。
長さ2.2メートルのパイプをいっぱいに出した状態と格納した状態では、約0.5~0.6秒の残響の差ができ、この残響の長さは演奏者の好みにより、電動で任意の位置に上下することができます。
ウィーンホールびいきでおなじみの、元ウィーンフィル首席コンサートマスター、ライナー・キュッヒル氏は、半分位の位置がお気に入りです。
『緞帳(花宴燦燦)』
お客様を迎えるホールの顔

ふるさとホールの緞帳は、世界各国の施設で40作の大壁画などを次々と完成させ、壁画作家として活躍中の、田村能里子氏の原画を基にして作られたもので、大きさは概ね縦8メートル×横15メートルです。
緞帳は舞台の前面にあり、開演と同時に開き(上がり)終演と同時に閉じる(降りる)豪華な装飾が施された舞台幕で、かつての緞帳は「緞帳芝居」と呼ばれ、定式幕(歌舞伎幕)を用いることを許された江戸三座の芝居に対して、格下の芝居小屋の代名詞でもありました。
現在のように緞帳が劇場の代名詞となった歴史は浅く、西陣綴織の緞帳が昭和26年大阪に登場してからのことです。今日では日本の緞帳も海外に輸出され、幕の用途以上に、美術工芸品としても評価されるようです。
『迫り・廻り舞台』
舞台がうごくと物語もうごく

ふるさとホールには、舞台床の一部を長方形に切り抜き、役者や大道具を奈落まで昇降させる機構「迫り」(正確には「迫り上がり舞台」)や舞台の床を丸く切り抜いた、文字どおりぐるりとまわる「廻り舞台」(「盆」とも呼ぶ)の機構が備えてあります。
舞台転換を迅速に行うことができる、大掛かりな「廻り舞台」機構を発明したのは歌舞伎なんだそうです。
「廻り舞台」も「迫り」も暗転や緞帳を降ろすことなく場面転換ができたり、これを利用した演出で感動的な舞台を作り上げたりできるスグレモノです。
(大迫り:7.2メートル×2メートル、小迫り:2.72メートル×1.21メートル)
(廻り舞台:直径11.8メートル 速度連続可変 最高速1周40秒)
『ステンドグラス』
ガラスからうまれる優美な輝き

ステンドグラスの起源は古く、古代ローマの時代からガラスの破片を組み合わせた窓などがつくられていたようです。ヨーロッパ各地の教会では、神の教えを物語にして表すステンドグラスがつくられました。現在では一般建築やインテリア、小物などに変化し、さまざまな場所で見ることができます。
ウィーンホールに入ると、木質系の素材で統一され、オーストリア製の18枚のステンドグラスで飾られた室内は暖かみがあり、魅惑の空間をつくり出しています。
『切戸口』
小さな戸口も大きな役割

ふるさとホールにセットできる能舞台には必ず右奥手に小さな出入口があり、これを切戸口といいます。
切戸口は狭く、しかも低く、人ひとりが屈んでやっと出入りできるくらいの大きさしかありません。
茶室におけるにじり口に似ています。
通常は後見などの出入口になっていますが、目立たないように退場したいときや登場したいときなどもここを使います。また、特に舞台上で殺された役の人たちなどが、ここから退場することから「臆病口」とも呼ばれます。